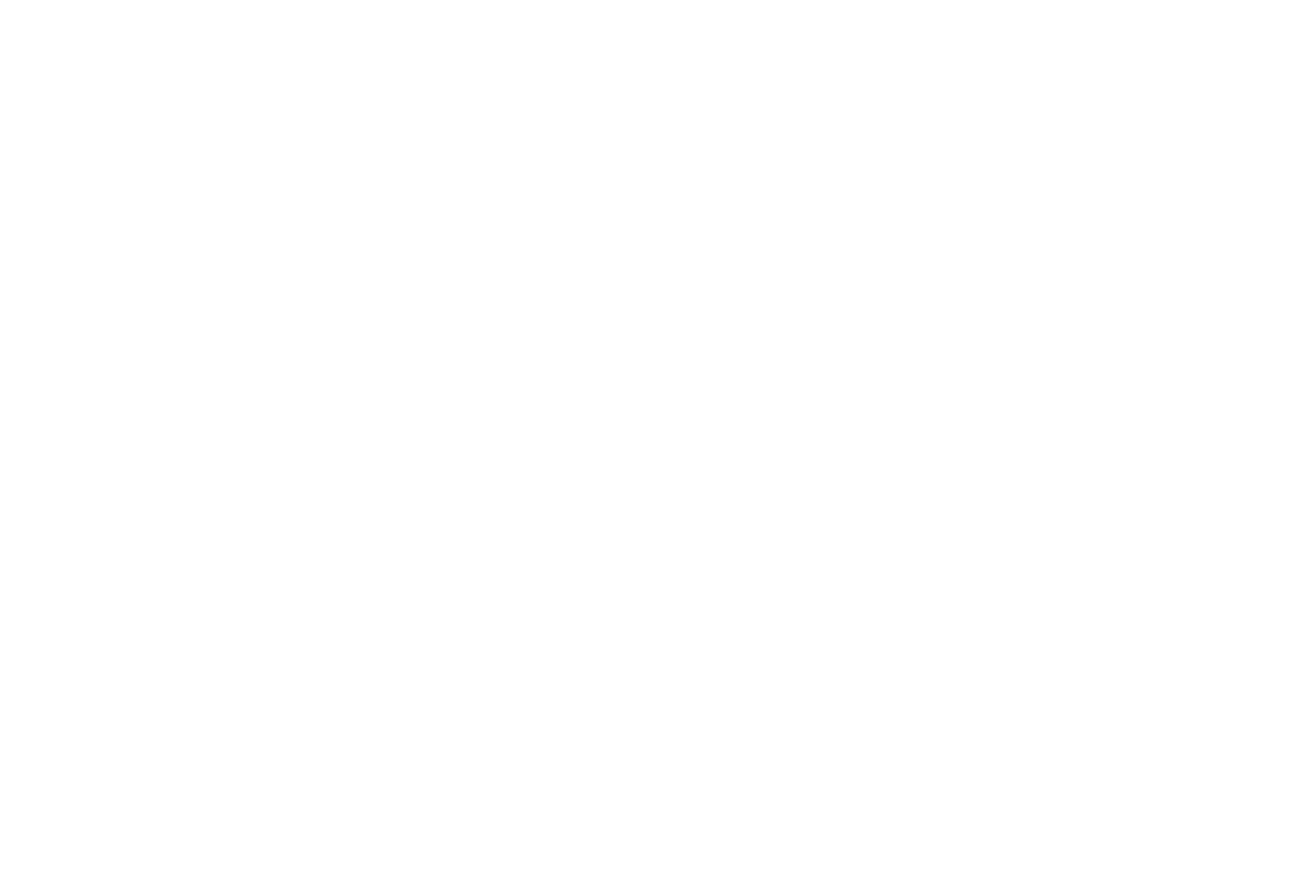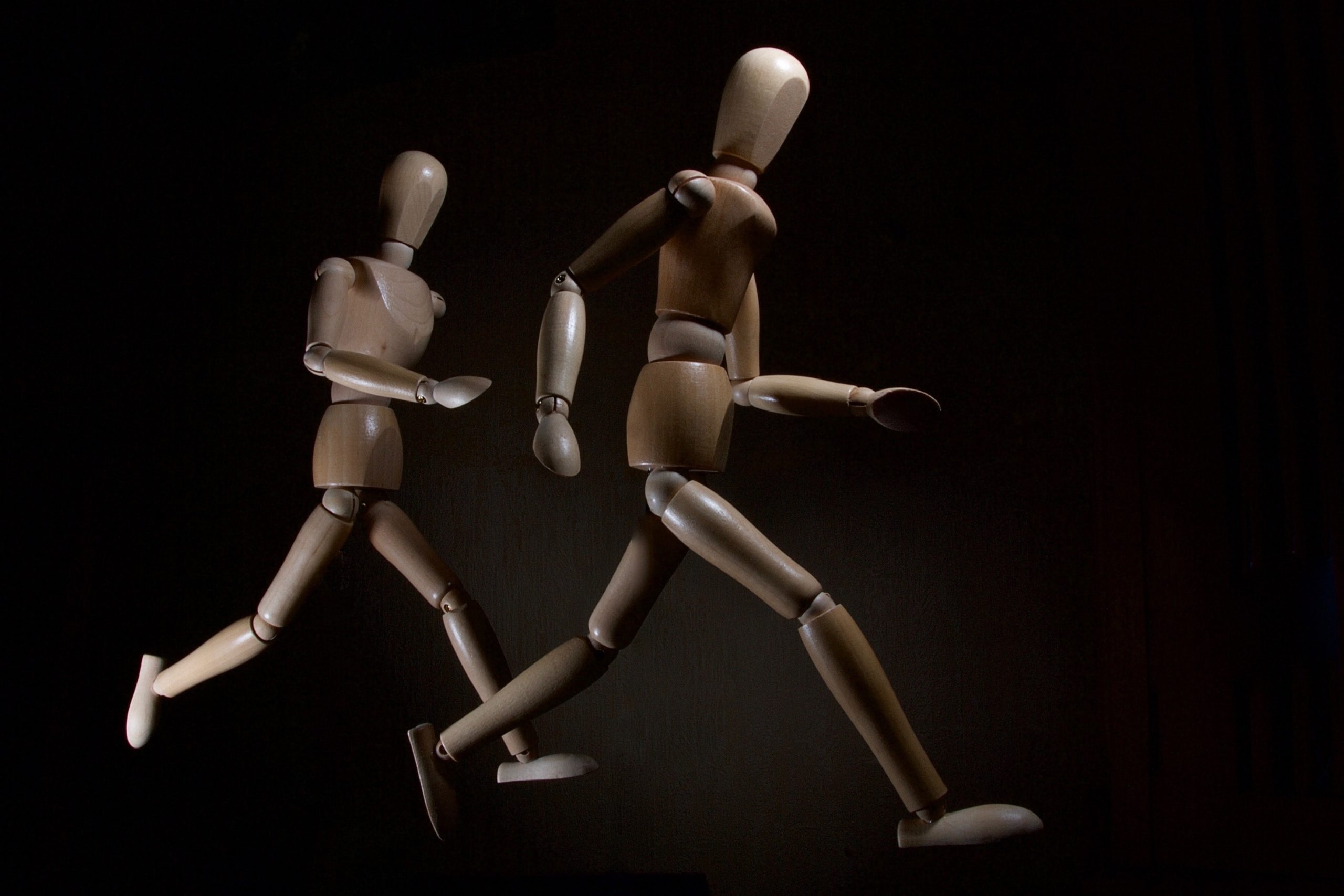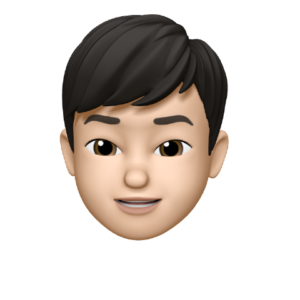
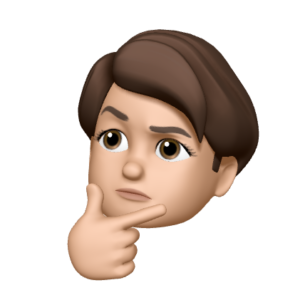
【本日の話題】
履物の歴史とランニング動作の変化
履物の歴史と人類の進化

我々人類は,何百万年も前から歩いたり,走ったりしてきました.履物が登場したのは3万年ほど前であり,当時は足の裏を保護するためのミニマムシューズが履かれていました.ファッショナブルな靴が最初に登場したのは100年以上前のことであり,現在我々が履いているようなクッション性のあるランニングシューズが市場に出まわり始めたのは,1970年以降とわりと最近のことです.
このように考えると,人間の進化の歴史と比べると履物の変化というのは非常に短い期間で急速に進んできたことがわかります.緩やかに進んできた人類における生物学的進化に対して,急速に進んだ文化的な発展は様々なギャップをもたらしました.その話題の中には,昔は存在していなかった,あるいは稀であった疾患がみられるようになったという話もあるようです.例えば,2型糖尿病や骨粗しょう症のどちらも,エネルギーの使い方や身体活動,現代の履物の急激な変化がもたらしたのではないかといわれています.
昔の人はどのように走っていたのか
 Flower photo created by teksomolika - www.freepik.com
Flower photo created by teksomolika - www.freepik.com
他の霊長類とヒトで違う点のひとつに足部のアーチを持つことがあげられ,このアーチは地形に応じて形や固さを調整することができることが知られています.これによりバネ(靱帯,腱膜,腱)を介してエネルギーを蓄積と放出ができるため,ランニング中の筋肉を効率よく使用することが可能となります.実際に,ヒトのアキレス腱の長さが他の霊長類に比べて10倍もの長さを持つのはこのためです.ランニング中のバネシステムと筋肉系の協調については,中足部から前足部での接地を用いることで,筋肉が遠心性収縮から求心性収縮に変わる際に,足部の伸長と反跳(反発)を利用することができることから最適であると考えられます.そのような背景から,人間はランニングシューズが発明される前には,中足部から前足部で接地して走っていた可能性が高いです.
現代人はどのように走るのか

現在では,レクリエーションレベルのランナーの約75%は後足部で接地して走っています.中足部から前足部接地と比べて足部での減速と反発をうまく使えない後足部接地で走ることは,接地時に加わる衝撃や負荷は大きくなっている可能性があります.しかし,ランニング障害の発生要因は多因子性でありランニング障害を負う人,負わない人が存在しています.実際に世界選手権のマラソンランナーもほとんどが後足部接地で走っています.現代では狩猟をしている民族はほとんどおらず,日常的にランニングを必要としない環境で過ごしています.狩猟をしている民族であっても後足部での接地で走っており最大でも5.0 m/sぐらいの速度です.裸足の子供たち(恐らく体重が軽いから)や走らない女性,柔らかな路面を走るランナーにも後足部で走る傾向が見られます.このように,履物だけでなく体重,成熟度,性別,ランニング経験,スピード,路面の状態なども接地パターンに影響を与えることがわかってきました.
(次回へ続く)
- 前足部から後足部にかけて接地することで,より効率よく走ることができると考えられる
- 昔の人は走る時に前足部で接地しながら走っていた(裸足やミニマムシューズ)
- 現代人は走る時に後足部で接地しながら走っている(クッション性のあるシューズ)
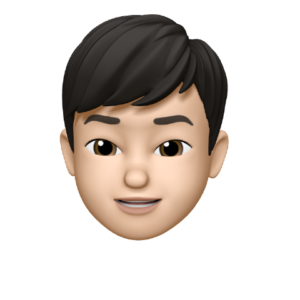
悩みは尽きませんね!次回は衝撃吸収に関わる様々な機能とランニング障害についてお話しできればと思います!
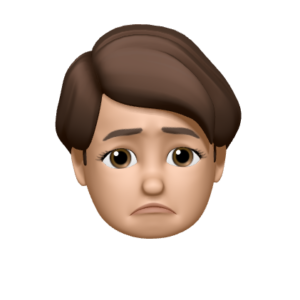
-

-
裸足(ベアフット)ランニングの話
続きを見る